人を中心にした“まちづくり”
バイオでまちを活性化。新潟県長岡市のバイオエコノミーとは(前編)

全国3位の米の収穫量(市町村別)を誇る新潟県長岡市。米を使った日本酒や味噌などの発酵醸造業も発達し、市内には16もの酒蔵があることから「発酵・醸造のまち」としてアピールしています。そんな長岡市が近年、持続可能な循環型社会をめざす「長岡バイオエコノミー」を推進し、「バイオのまち」へと進化しようとしています。
バイオエコノミーとは、化石燃料の代わりに生物資源やバイオテクノロジーを活用し、持続可能な経済成長を実現すること。2009年にOECD(経済協力開発機構)が提唱したのを機に世界で広まり、日本でも2019年に「バイオ戦略2019」を策定。2030年までに世界最先端のバイオエコノミー社会を実現することを目標としています。今回はそんなバイオエコノミーをいち早く推進する長岡市の現状と、長岡市がめざすまちの未来像を前後編にわたりご紹介します。
(取材時期:2023年9月)
目次
- 生ごみバイオガス発電の成功がバイオエコノミー推進のきっかけに
- 微生物の力で田んぼを守り「米どころ長岡」を活性化
- 大学と企業が連携し、米を地域内循環させる「N.CYCLEプロジェクト」
- 生ごみからバイオ肥料も。広がり、進化する地域内資源循環
生ごみバイオガス発電の成功がバイオエコノミー推進のきっかけに

生ごみバイオガス発電センターを運営する長岡バイオキューブの景山兼之介さん。右の丸い建物がバイオガスを保管するガスホルダー
長岡市は長岡バイオエコノミーを掲げる以前から、資源循環に取り組んできました。発端は、可燃ごみを焼却したあとの焼却灰を埋める最終処分場の残余容量が逼迫したこと。処分場を延命すべく2004年からごみの大幅削減に乗り出し、資源物の分別収集、家庭ごみの一部有料化に着手。さらに生ごみ資源化の準備を進め、2013年には「生ごみバイオガス発電センター」の稼働を開始。市内から集めた生ごみを微生物分解し、発生したメタンガスで発電することにより、生ごみのエネルギー化に成功しました。
「そもそも、きちんと分別された生ごみがこれだけ集まるのがすごいことだと思うんです」と話すのは、長岡バイオエコノミーを担当する長岡市役所の宮島義隆さん。施設をつくっても、生ごみが集まらないことには生ごみバイオマス化はできません。稼働開始から10年間、施設が継続稼働できているのは、市民による丁寧な生ごみ分別のおかげなのだといいます。
生ごみバイオガス発電センターの運営会社、長岡バイオキューブの景山兼之介さんによると、長岡市(行政)が生ごみの分別収集についての市民への周知を、説明会や情報誌などを通して、定着するまで根気強く繰り返し行ったといいます。その甲斐あって現在では、年間約1万トンの生ごみから、約240万kWhの電力を発電し、一般家庭の500世帯分が1年間に使用する電気量に相当する、約212万kWhの電力を電力会社に送電しています。

長岡バイオエコノミーを担当する長岡市役所 長岡市商工部産業イノベーション課の宮島義隆さん
「廃棄される未利用資源を回収し、資源化する仕組みづくりには市民の協力が不可欠です。生ごみバイオガス化の実績は、長岡市なら資源循環型社会を実現できるという自信につながりました」と宮島さんは語ります。
住民の環境問題や資源循環への高い意識をはじめ、長岡市にはバイオエコノミーを推進する条件がそろっていました。発酵・醸造という古くからのバイオテクノロジーの蓄積。市内に4つの大学と高専があり、バイオをはじめとする最先端テクノロジーの研究も盛んなこと。食品、機械といった、ものづくり産業の発達など。そこへバイオエコノミーの世界的な広まりが後押しとなり、資源循環で産業イノベーションを起こそうとする機運が上昇。その第一歩を踏み出すべく、長岡市は2020年、市内の大学や高専、地元企業などと一緒に「長岡バイオエコノミー・シンポジウム」を開催。産学官連携によるバイオエコノミーの取り組みをスタートさせました。
微生物の力で田んぼを守り「米どころ長岡」を活性化
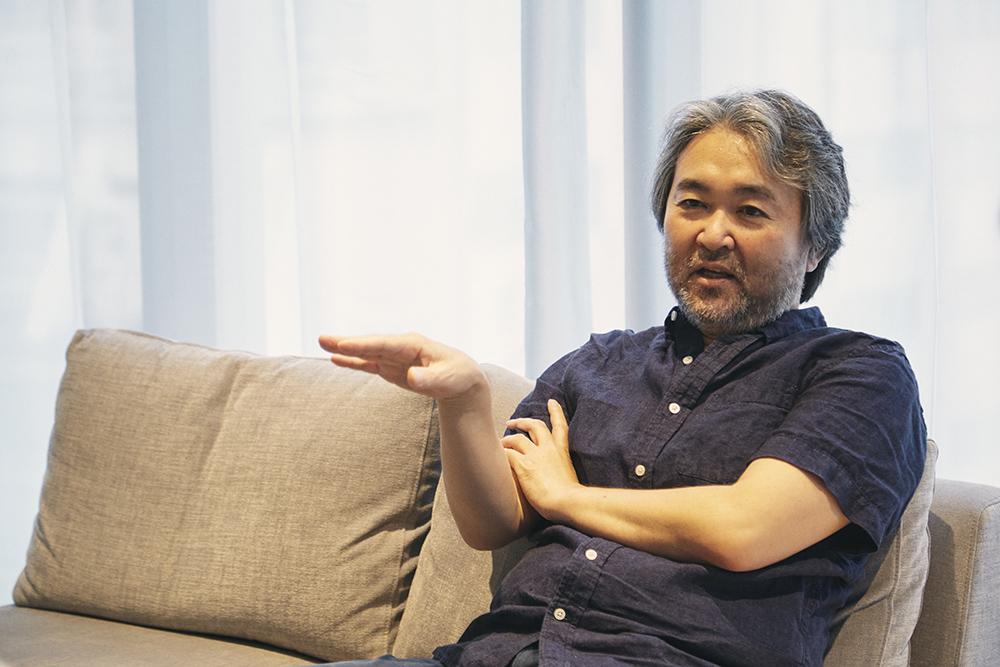
長岡バイオエコノミーの推進者、長岡技術科学大学の小笠原渉教授
米、発酵をキーワードに長岡バイオエコノミーを牽引するのは、応用微生物学を専門とする長岡技術科学大学の小笠原渉教授。発酵の可能性について次のように説明します。
「発酵は全て微生物のはたらきによるもので、昔から活用されてきたバイオテクノロジーです。発酵といえば味噌や酒などの発酵食品がメジャーですが、発酵によってつくられるのはそれだけではありません。食品加工残渣などから、たんぱく質や食用油脂をつくることだってできますよ」
微生物はほかにも、医薬品や化粧品、エネルギー、素材の生産など幅広い分野で利用されています。しかも微生物による生産は化石資源による生産よりも環境負荷が低く、持続可能な未来に大きく貢献すると考えられています。そんな微生物の力を活用し、「米どころ長岡」の魅力と存在感を高め、長岡市の活性化をはかりたいと小笠原教授は構想しています。
「全国の耕地面積あたりの田んぼと畑の割合をみると、全国平均がほぼ半々なのに対し、長岡市は9割が田んぼ。圧倒的に米づくりのまちなんです。だからこそ酒や米麹を使った味噌、米菓など米の食品加工業も栄え、米を保存、活用する知恵として発酵・醸造の技術も発達し、棚田や平野に広がる美しい田んぼの景観も生まれたのです。こうした長岡の米づくり文化は、国内外から人を呼び込めるポテンシャルを持っていると考えています」
一方、そこには課題もあるといいます。農機具や肥料の高騰、米価格の下落、後継者難など、米農家の現状は厳しく「このままでは田んぼが消えてしまいかねない」と懸念する小笠原教授。田んぼが消えれば食品加工業も衰退し、働く場が失われ、労働力人口が流出し、まち全体が弱体化してしまいます。
そこで小笠原教授は、研究を活用して持続可能な農業を実現しようと、さまざまな取り組みを行っています。その1つが、長岡技術科学大学と地元企業4社が共同で始めた「N.CYCLEプロジェクト」。米の生産、加工の工程では、洗米水や酒粕、もみがらなど米由来の廃棄物が大量に発生しますが、そのほとんどが焼却処分されています。これらを資源として地域内で循環させ、長岡米のブランド化をはかる試みです。
大学と企業が連携し、米を地域内循環させる「N.CYCLEプロジェクト」

せんべいやおかきなどの米菓メーカー、岩塚製菓株式会社。多くの米菓メーカーがコスト削減のために輸入米を使用するなか、100%国産米を使用しています。輸入米は米粉や精白された状態で輸入され、米の風味や香りがとんでしまうというのがその理由です。
せんべいなどの製造は、加工直前に玄米を精白し、米を洗うところから始まりますが、その過程で発生するのが大量の洗米水。家庭で出る米の研ぎ汁と同じ、白濁した水です。最終的には濁り成分だけを集めて汚泥として処分されますが、汚泥といっても本来は、米由来の栄養分のかたまりです。そこでN.CYCLEプロジェクト(Nサイクル)は、洗米水の有機成分を微生物の力で凝集、これを堆肥化し、稲作の有機肥料として再利用するサイクルを推進しています。長岡技術科学大学の志田洋介准教授は、N.CYCLEのポイントを次のように説明します。
「これまでは岩塚製菓さんで出た汚泥を、ホーネンアグリさんで園芸用肥料にリサイクルしていましたが、凝集には化学薬品が使われていました。ケミカル成分が含まれると有機JAS認証を受けることができないため、稲作には使えなかったのです。これを環境にやさしい微生物凝集に代え、洗米水のような未利用資源を田んぼに還すサイクルを構築したのがN.CYCLEです」
微生物凝集技術を提供するのは長岡技術科学大学。凝集した有機成分を堆肥にするのは、農業や園芸用の土づくりメーカー、株式会社ホーネンアグリ。有機肥料を再利用するのは、県内のJAで最大規模のJAえちご中越。そしてプロジェクトをコーディネートするのはデザイン会社の株式会社ネオス。専門分野の異なる地元の企業や大学が連携し、それぞれの強みを活かすことで米の地域内循環を成立させています。

左から、岩塚製菓株式会社の村松悠さん、畳谷和之さん、株式会社ホーネンアグリの小林ひかりさん、JAえちご中越の石塚慎治さん
岩塚製菓の畳谷和之さんは「小笠原教授と出会い、日々捨てていた洗米水を価値あるものへと転換できることに気づいたところから始まった」と、プロジェクト立ち上げ時を振り返ります。
「大切な米から生じた洗米水を肥料として有効活用することで、良質の米ができて農家の収入増となれば、こんなに良いことはありません。農家の方たちがあっての岩塚製菓ですから、何としても田んぼを守らなければとの思いで参加しています」
JAえちご中越の石塚慎治さんは、プロジェクトの意義をこう語ります。
「私たちJAは岩塚製菓さんにお米を納めさせていただいています。つまり岩塚製菓さんの洗米水は、私たちの田んぼから生まれたもの。田のものを田に還す、本来の地域循環型農業を実現することに大きな意義を感じています。また、これは長岡に限りませんが、近年、田んぼの地力低下が危惧されています。資材費高騰や労働力不足などから、秋の土づくりに取り組むことができない農家が増えています。洗米水の肥料には稲を丈夫にするケイ酸が豊富に含まれており、地力の向上が期待でき、継続使用することで米の品質と収量を安定的に確保できればと考えています」
ホーネンアグリの小林ひかりさんも、異常気象のリスクが高まるなか、田んぼの地力をあげることがこれまで以上に重要だといいます。
「農家の方には、栄養豊富な洗米水の肥料で良い土をつくり、丈夫な稲を育て、秋に安定して良い米を収穫していただきたい。それが岩塚製菓さんのおいしい米菓づくりに、そして翌春また、私たちの土を使って田植えをしていただくことにもつながりますから」
生ごみからバイオ肥料も。広がり、進化する地域内資源循環

2023年からは、JAえちご中越の3軒の農家がN.CYCLEの肥料を使用し、効果の検証を開始。これと並行し、長岡技術科学大学は稲作に有用な微生物を活用した高機能堆肥の研究開発にも取り組んでいます。最終的にめざすのは、化学肥料から微生物肥料への完全代替です。JAえちご中越の石塚慎治さんは期待をこめてこう語ります。
「JAえちご中越は現在、化学肥料と化学合成農薬を5割以上削減した特別栽培米の栽培に取り組んでいますが、無化学肥料栽培米はそれを上回るもの。成功すれば、環境にやさしい安心安全な米として高付加価値化が期待できます」
また、ネオスの山本嗣也さんは「地域内循環から生まれた米は、その取り組み自体も価値になる」といいます。
「N.CYCLE米を長岡のブランド米として市内外にアピールし、都会の方たちにも田んぼの循環について知ってもらう機会にしたいですね」

N.CYCLEプロジェクトをコーディネートする株式会社ネオスの山本嗣也さん
一方、ホーネンアグリの小林さんは、N.CYCLEの取り組みをより多くの地域の人たちに伝えることも大切だといいます。
「特に知ってほしいのは若い方たち。循環型の商品や活動が当たり前なまちの未来につなげてもらえたら。N.CYCLE米を給食や食育に活用するなどして、伝えていきたいです」
岩塚製菓の村松悠さんは資源循環に携わり、こんな変化を感じているそうです。
「これまで自社のことしか分からなかったのが、資源循環の輪に加わることで地域の人たちとのつながりが生まれ、地域について知ることもできました。何より大きいのは、地域の人たちと顔が見える関係が築かれ、『地域のために』という思いがより強まったこと。資源循環の取り組みを通して学ぶことがたくさんあります」
長岡市では、米以外にも未利用資源の循環が進んでいます。生ごみバイオガス発電では年間約400トンの発酵残渣が生じ、これまで燃料補助剤として利用されていましたが、2022年からは肥料としての効果を確認するため実証試験を開始。「大規模農家の方から好評いただいている」と、長岡市役所の宮島さんは顔をほころばせます。
「こうして少しずつ、資源循環に興味を持つ方が増えていることがうれしいです。バイオ肥料としての製造販売も視野に入れつつ、まずは市内の利用拡大をはかり、市民のみなさんを巻きこみながら、資源循環のさらなる普及を促進していきます」
多様なステークホルダーが協力して進めている長岡バイオエコノミー。そこから見えてくるのは、産学官の円滑な連携です。記事の後編では、長岡市がどのようにバイオエコノミーを推進しているのか、産学官の連携のあり方や、プロジェクトを生み出す場づくりの工夫、そしてバイオエコノミーを始めるヒントをご紹介します。