人を中心にした“まちづくり”
“色”から地域を再発見。大分県「地域の色・自分の色」研究会の活動

地域の人たちには当たり前すぎて、気づかれないまま埋もれている地域資源。それを地域ぐるみで「色」という視点から掘り起こし、教育や地域振興に活かそうとするユニークな取り組みが大分県で行われています。活動を推進するのは「地域の色・自分の色」研究会。「色」を切り口にした地域づくり、地域・行政・教育機関との連携協力のあり方とは?前後編にわたってご紹介します。
目次
- “色”という視点から地域の魅力を再発見する
- 地域の人々・教育・行政をつなぐ中間組織(リエゾン)をめざす
- 教材制作にあたって地域の農産物・七島藺(しちとうい)に着目
- 貴重な地域資源を次世代に伝える重要な役割として
“色”という視点から地域の魅力を再発見する
学習院大学の秋田喜代美教授の監修のもと、2014年4月から大分県を拠点に活動する「地域の色・自分の色」研究会。子どもたちに“色”を通して地域の自然や歴史文化を学んでもらい、地域の素晴らしさを再発見してもらうべく、独自のふるさと学習を大分県の小学校、幼稚園・子ども園で展開しています。
「どの地域にも宝物はあるはず。それを“色”から探そうというのが、活動の原点なんです」と語る研究会代表の照山龍治さん。活動を始めたきっかけを次のように話します。
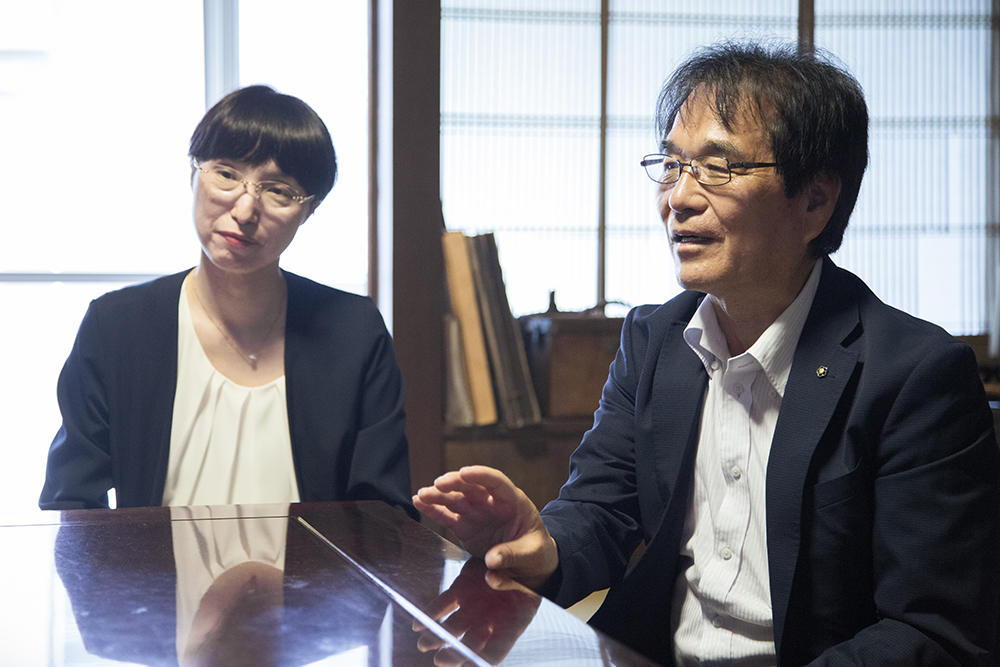
画像右が研究会代表の照山さん。画像左は研究会の事務局を担当する塩月孝子さん
「私は大分県庁に長年勤め、県の防災、教育、医療、文化の保護振興など、さまざまな現場を経験しました。そこで感じたのは、多くの自治体職員や教育関係者が、地域のことを知っているようで知らないということ。これでは地域活性化はもちろん、地域における多くの取り組みがうまくいかないのではと感じたのです」
例えば、照山さんが東日本大震災後、大分県の地域防災計画の見直しを担当したときのこと。津波被害箇所を調査するため、県内外の海岸を回っていた照山さんは、いたるところで古い石碑を見つけたそうです。それは昔、津波に遭った先人が「ここまで津波が来た」「これより下に家を建てるな」と後世に伝え遺したもの。そうした石碑は今となっては草に埋もれているものも多く、先人の教えが省みられていない現実を目にしたと言います。
「私たちが普段気づかないだけで、地域には大切なもの、素晴らしいものが実はたくさん埋もれているのではないか。地域に暮らす人たちが地元の自然、歴史、文化に目を向け、埋もれている地域資源を掘り起こして有効活用する。それこそが本当の意味での地域振興だと思うに至ったのです」
地域の素晴らしさを一番知ってほしいのは、地域の未来を担う子どもたち。子どもたちに地域の素晴らしさをあらためて学んでもらうことで、教育はもちろん、地域振興にもつなげていく。こうして研究会の「色を通したふるさと学習」の取り組みがスタートしました。“色”というテーマに着目した理由を照山さんは次のように語ります。
「色を切り口にしたのは、単純にわかりやすいからです。子どもの興味関心を惹きやすく、子どもからお年寄りまで、世代を問わずその価値を共有できるのも大きな利点だと思いました」
地域の人々・教育・行政をつなぐ中間組織(リエゾン)をめざす
「地域の色・自分の色」研究会のメンバーは、元県庁職員、教員、学識者などの有志から構成されています。地元の人々や行政・教育機関とも協力連携しながら、地域ぐるみのふるさと学習と地域振興を推し進める中で、研究会が担っているのが「中間組織(リエゾン)」としての役割。照山さんは次のように語ります。

「地域の人たちから『地域の資源を子どもたちの教育に活用してもらえたらうれしいが、学校とのつながりがない』という声をよく聞くことがありました。同時に『地域と連携して何か一緒にやってみたいが、さまざまな調整が難しい』という学校側の声も。そこで両者の間に入り、つなぎ役、橋渡し役、仲介役を担うのが私たち研究会の中間組織(リエゾン)としての役割です」
同じ地域に暮らしているといえども、住民、教育、行政ではそれぞれの立場も異なり、考え方や価値観も違います。立場の異なるもの同士をつなぐのは、そう簡単なことではないと照山さんは言います。
「例えば、企業は経営(年次決算)、行政は政策(2〜3年後の事業成果)、教育現場は子どもの成長(10年、20年後の子どもたちの姿)を考えます。また、地域ぐるみで子どもを自由に育てたいと考える人もいれば、子どもの安全を第一と考える人もいます。このように、子ども中心の地域づくりには、いろいろな価値観を持った団体や人々が関わってきます。そんなときに、私たちが間に入って根気強く対話を重ねながら、融和をはかる。多様な意見をもみあわせ、新しい価値やアイデアを生み出していく。そんな“界面活性剤”や“触媒”としての機能に、研究会の存在意義があると思っているのです」
加えて、研究会が活動を行う中で大切にしているのは、草の根からのボトムアップ式で地道に広めること。トップダウン式の活動はスピードも速いかもしれませんが、協力者たちの“やらされ感”も強くなってしまう。自身の経験談も踏まえて、そのように照山さんは語ります。
「例えば学校へ協力を仰ぐ際にも、研究会が教育長や校長に最初にアプローチするのではなく、まずは研究会の理念に共感して『やってみたい』と思った教員主導で、自分のクラスで実践してもらい、それを見た他のクラスの教員が『自分もやってみよう』と実践する。そのようにして教員から他の教員、他の学年、学校全体へと広がり、さらに子どもから家庭へ、家庭から地域ぐるみの取り組みへと広がっていくのが理想です。時間はかかりますが、トップダウン式でやるよりも、結果的に広がりや持続性は高いと考えています」
教員や子どもたち、活動に携わる人々の「やってみたい」という主体的な気持ちを大事にし、研究会はその気持ちを形にする中間組織(リエゾン)として環境整備に徹する。研究会の活動を持続可能な取り組みにしていくために重要なことだと、照山さんは強調します。
教材制作にあたって地域の農産物・七島藺(しちとうい)に着目
「地域の色・自分の色」研究会は地域の歴史や文化、自然について学べる教材を制作し、実践校や県内の図書館、幼稚園、小中学校などに配布しています。これも研究会の主要な活動の一つですが、そこで欠かせないのが地域の協力パートナーとの連携です。教材制作にあたっての研究会の協力パートナーに「くにさき七島藺振興会」(大分県国東市)があります。国内でも大分県北東部の国東地域でしか生産されない希少な農作物、七島藺(しちとうい)の振興をめざし、活動する団体です。

七島藺が栽培されている畑の様子
「七島藺はまさに大分県の隠れた地域資源。くにさき七島藺振興会の方々に研究会の取り組みをお話したところ、ぜひ一緒にやりましょうとご賛同いただき連携に結びつきました。七島藺の株を教材として協力校にご提供いただき、実際に子どもたちに栽培体験をしてもらったり、教材の制作にもご協力いただいたりしています」と照山さんは話します。
七島藺は、い草と同じく畳表の原材料となるもの。高級畳として知られる「琉球畳」は、畳表に七島藺を使用した畳を指します。大分県には360年ほど前に鹿児島県のトカラ列島から伝わり、七島藺で織りあげられた畳表が大分の特産物として全国に出荷されるようになりました。七島藺を用いた畳は現在では希少価値が高くなっていますが、その丈夫さから古くは農村や庶民の家でも広く使われていたそうです。くにさき七島藺振興会の林浩昭会長は、かつての国東地域についてこう振り返ります。

くにさき七島藺振興会・林浩昭会長
「一帯に広がる七島藺の田んぼといえば、国東の原風景でした。子どもたちもよく田植えや収穫の手伝いをしたものです。特に、七島藺の茎を縦方向に割く作業の辛さは、この地域で育った人々の記憶に染みついています。七島藺から得た収入のおかげで、子どもを大学まで行かせることができた、という家庭も多かったように思います」
かつては多くの七島藺農家が存在した国東地域ですが、昭和30年頃をピークに生産農家は減り続け、2023年現在は7軒の農家が栽培するのみとなりました。優れた耐久性と香り、美しい自然の風合いをあわせ持つ七島藺の畳は、全国に根強いファンがいるものの、現在は地元でも知る人ぞ知る存在となっていた現状があったといいます。

茎を二分割して乾燥した七島藺。刈り取ったばかりの茎の断面は三角形をしている
貴重な地域資源を次世代に伝える重要な役割として
くにさき七島藺振興会の発起人で、事務局長を務める細田利彦さんは「地域の色・自分の色」研究会に協力する理由をこう話します。

くにさき七島藺振興会・細田利彦事務局長
「伝統文化は一度消えてしまったら、復活させることは本当に難しい。七島藺が消えたら、何百年と続く一つの日本文化が消えてしまうことになる。そうならないよう、私たち振興会はありとあらゆる手段で次世代に残そうとしているわけですが、研究会と連携することで、教育という側面から子どもたちに七島藺の存在を伝えていくことは、非常に意義深いことだと思いました」
七島藺の株を小学校に教材として提供してくれたのは、地元では数少なくなってしまった七島藺生産農家の1人である松原正さん。貴重な七島藺の株を提供するにあたって、次のような思いを託したそうです。

国東市で七島藺を栽培する松原さんご夫妻
「最初は『これって何の草や?』みたいなところから、七島藺という名前を覚えてもらって、実際に育ててもらって。そうやって七島藺にふれた体験が、子どもたちの人生のどこかに生きていてくれるとうれしいですね。ふとしたときに思い出したり、ちょっとだけ七島藺を暮らしに取り入れてみたり、そんな風な存在になったらありがたいです」
七島藺を教材に取り上げるにあたり、林さんは照山さんと話し合い、テーマを「変化する色」に設定したと言います。
「七島藺は田んぼに生えているときは緑色ですが、刈り取って乾燥させると青緑、畳表になると青みがかった銀色になります。さらに20年、30年と使い込んでいくうちに艶が出て、美しい飴色に変わるんです。いわば自然の色から暮らしの色、家族の歴史の色に変わっていく。そうした色の変化を通して、七島藺の歴史文化、ふるさとの隠れた文化を知ってもらい、七島藺の価値に気づいてもらうのが狙いです」

まだ新しい七島藺の畳。緑色に近いが経年変化で飴色に変わっていく
こうして教材という形で、七島藺の価値を次の世代に伝えることには資料性・記録性の意味でも大きな意味があり、それが実現できたのは、中間組織(リエゾン)となって学校や教育委員会、地域を巻き込んでいく「地域の色・自分の色」研究会の存在があったからこそだと林さんは語ってくれました。
では子どもたちは、こうした教材を使いながら、実際にどのような学びを行なっているのでしょうか? 記事後編では色という視点から「ふるさと」について学ぶ、教育現場での実践についてご紹介します。
