アドバイザー活動紹介
手術室の抱える課題を克服し
時間と空間を越えて最適な医療を提供する
医療の高度化にともない、手術室は、多種多様な医療機器が集積する一大センターとなっている。一方、現場では、医療機器に起因するヒヤリ・ハットに関する指摘もある。こうした中、医工連携の取り組みにより、世界に先駆けてスマート治療室「SCOT®(スコット)」を開発したのが東京女子医科大学
先端生命医科学研究所の村垣
善浩氏だ。SCOTによって、医療はどう変わっていくのか──。また、持続可能な社会の実現、ひいては私たちの健康管理にどのような価値を提供するのか──。SCOTを通じて村垣氏が描く医療の未来の姿、そこから見えてくる「これからのまちづくり」の在り方を聞いた。
(取材時期:2020年7月)
目次
- 手術室を1つの大きな医療機器として再定義
- 医療機器の問題が多くのヒヤリ・ハットにつながっている
- プロトタイプによる価値の見える化でプロジェクトが加速
- 時間と空間を超えて最高のチーム医療を実現できる
- 異分野の人同士の「知の紡ぎあい」に大きな期待
手術室を1つの大きな医療機器として再定義
私たちの安全・安心な生活を支える重要なサービスである医療。新しい技術や薬品によって、かつての難病が根治可能になるなど、医療は、日々、進化を続けている。
その進化が端的に表れているのが手術室である。入室したことはなくとも、テレビドラマなどを通じて見る手術室には、内視鏡や人工呼吸器など、先人達の知恵の結晶であるさまざまな医療機器が集積している。
この多様な機器が設置された手術室を再定義し、新しい提案によって、次の進化を牽引しているのが東京女子医科大学の村垣
善浩氏だ。

東京女子医科大学 先端生命医科学研究所 副所長・教授
メディカルAIセンター センター長 村垣 善浩氏
1986年神戸大学医学部卒業、1992年より3年間米国ペンシルベニア大学病理学教室に留学し、2011年より現職。悪性脳腫瘍の治療を専門とし、医療機器開発にも取り組んでいる。術中MRIを核とするインテリジェント手術室の分野では2000例のチーム臨床実績をもち、2010年には科学技術政策担当大臣賞を受賞。医工学連携に注力し、医療のIT化やロボットの導入に尽力している。厚生労働省や経済産業省の各種委員を務め、政府への提言も積極的に行っている。
「これまで、手術室は、多数の機器が設置された手術のためのスペースでした。しかし、エンジンやハンドル、計器など、『移動』という目的のためにさまざまな装置が組み合わさったクルマのように、手術室もまた『治療』という目的を持つ1つの大きな医療機器と考えるべきではないか──。そう考えて、スマート治療室『SCOT(Smart Cyber Operating Theater)』を開発しました」
医療機器の問題が多くのヒヤリ・ハットにつながっている
村垣氏の気付きの背景には、医療の現場を震撼させたある論文がある。論文上で、手術におけるヒヤリ・ハットやインシデントの3~4割が、機器間の相性や設定ミスなど、医療機器の問題に起因しているというデータが発表されたのだ。
「実際、思い当たる節はありました。いまだに“昭和生まれ”の医療機器が幅を利かせているし、同じ種類の医療機器を何台も保管しているケースも少なくありません。例えば、内視鏡1つをとっても、ある医師はA社製のもの、別の医師はB社製という具合に、医師によって“好み”があるからです。看護師や臨床検査技師は、苦労してさまざまな機器の扱いを覚えなければなりません」
また、他分野に比べて医療分野はデジタル化が遅れているという指摘もある。例えば、クルマのダッシュボードには、スピード、回転数、エンジンルームの温度、ガソリンの残量などを示すメーターが1つにまとめられている。企業ITでもさまざまなシステムのデータを統合し、可視化することは、ごく当たり前になっている。一方、手術室の医療機器が出力するデータはバラバラの状態。連携は進んでおらず、共有はスタッフの口頭での読み上げが基本だ。時に時間との闘いを強いられる手術において、このことは正確性、安全性、効率性の低下要因にもなりかねない。
SCOTはこのような課題を解決する。IoTを活用して各種医療機器や設備を接続し、手術の進行や患者の状況を統合的に把握することで、手術の精度と安全性を向上させるのである。現在、東京女子医科大学と国立研究開発法人日本医療研究開発機構(AMED)が中心となり、信州大学、広島大学、東北大学、鳥取大学などの大学と企業11社が参加して、研究開発と臨床研究が進められている。
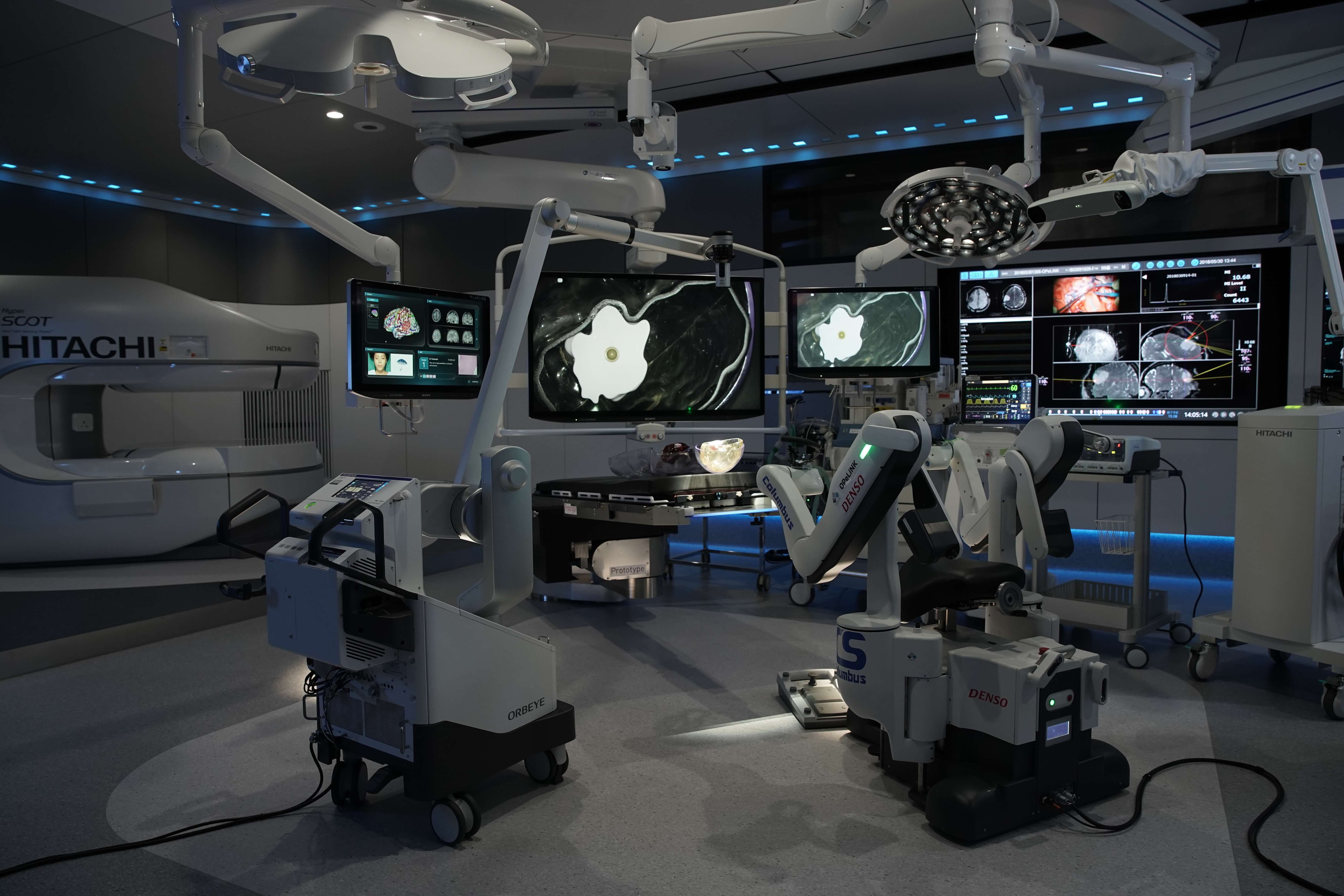

スマート治療室SCOT®
従来、それぞれが独立していた20以上の医療機器や設備をネットワーク(OPeLiNK®)で接続することで、時間同期した、術中情報を統合表示することで手術の進捗や緩徐の状況をすぐさま把握できる
プロトタイプによる価値の見える化でプロジェクトが加速
SCOTの開発プロジェクトがスタートしたのは2014年のこと。だが、プロジェクトは発足当初から壁に突き当たった。
前述したように、医師は医療機器に対するこだわりがあり、優秀な外科医の多くは、その繊細な手技を支える、自分だけの「名刀」を持っているものだ。その選択権を外科医から取り上げるのは至難の業だ、というのが大方の見方だった。
無論、SCOTがめざすのはスマート治療室という1つのシステムを構築することであって、その名刀を取り上げることが目的ではない。「ガラケーしか持っていない人に、『スマホの何がすごいのか』を理解してもらうのは難しいですよね。それと同じで、スマート治療室が存在していない当時、SCOTとは何なのか、医療機器をネットワークでつなぐことによって何が実現するのかということを、なかなか理解してもらえませんでした」。
「百聞は一見にしかず──。状況を打破するには、実物を見てもらうしかない」。そう考えた村垣氏は、2016年にプロトタイプを開発し、東京女子医科大学に設置。誰でも一目でSCOTの価値を理解できるようにした。この取り組みは、大いに奏功し、SCOTに対する理解度は一気に向上。「プロジェクトを前に進めるための価値の見える化の重要性を学びました」と村垣氏は振り返る。
理解が広まったSCOT開発プロジェクトは、ここから一気に加速。2016年春には、術中MRIを中心とする医療機器をパッケージ化したエントリーモデル「ベーシックSCOT」が完成。同年6月、その第1号が広島大学病院に導入された。
次いで、このベーシックSCOTを基に、手術室のほぼすべての機器をネットワークで接続可能にした「スタンダードSCOT」も完成。2018年7月に信州大学病院に設置され、脳神経外科で臨床研究がスタートした。
そして、2019年5月には最上位モデルとなる「ハイパーSCOT」が東京女子医科大学病院に導入された。新規開発のロボットヘッドによるロボット化やAIによる手術ナビゲーションの開発と並行して、臨床上の有効性を確認するための研究が脳神経外科で進められている。
時間と空間を超えて最高のチーム医療を実現できる
「時間と空間の制約を超えて、いつでも高いレベルの手術ができる」村垣氏は、SCOTの価値をこう説明する。
例えば、担当の専門医が学会などで不在の時に、患者の容体が急変してしまった。このような場合でも、SCOTがあれば、担当医は外出先から意思決定に必要なすべての情報を確認して判断を下し、現場の医師たちによる緊急手術をサポートできる。「SCOTの『戦略デスク』は、ネットワークに接続されたすべての医療機器の情報を統合的に見ることができます。ここにネットワークを通じてアクセスすれば、見ている情報は手術室にいるのと同じ。いつでもどこでも、手術のための適切な意思決定を行えます」(村垣氏)。
また「どのような状況であれ、最高のチームを組むことができる」ことも大きな価値だと続ける。
近年は医療の専門化が進み、ひと口に脳神経外科といっても、脳血管障害や良性脳腫瘍、悪性脳腫瘍など、細分化が進んでいる。本来は疾患に応じて、その分野に特化した医師が執刀医を務めることになるが、地域によってはそれぞれの専門医がおらず、都市部の病院に搬送するしか方法がないことも少なくない。
こんな時、SCOTを利用すれば、執刀医の専門外の疾患であっても、その分野の専門医と情報を共有し、助言を仰ぎながら手術を行うことができる。「いつでも、どこにいても最高の医師たちの助言を受け、最高の手術を実現することができるのです」と、村垣氏は、医療の地域間格差の解消、地球規模のチーム医療を実現する可能性について語る。
5Gを活用した「モバイルSCOT」の開発も進んでいる。2019年11月には、広島大学とNTTドコモ中国支社が実証実験を実施。5G回線を通じて大容量の手術データを送受信し、医師が遠隔で手術を支援する実験を行った。「モバイル版が実用化されれば、災害救急の現場で脳外科手術が必要になっても、現場の救急医と遠隔地の脳外科医がタッグを組み、最高レベルの治療をすることができます」(村垣氏)。SCOTを通じて、宇宙ステーションの飛行士の治療を行う。そんな未来がすぐそこまで来ているのだ。
異分野の人同士の「知の紡ぎあい」に大きな期待
ほかにも、新型コロナウイルスが浮き彫りにした課題の1つである医療従事者を保護するオンライン診療態勢の充実。住民一人ひとりの日々の健康情報や医療情報を集約して実現する、疾病リスクの早期発見、検診・診断から治療までがワンストップになった最適な医療の提供など、SCOTにはさまざまな可能性がある。
「今、医療はインフォームドコンセント(説明した上での同意)をさらに進めた、インフォームドディシジョン(情報に基づく患者の決定)の時代。治療の選択肢がいくつかある場合、どの治療を選んでもリスクは付いて回ります。SCOTに蓄積したデータを使って、ベネフィットとリスクについての情報を可視化できれば、患者さん自身が自律的に治療を選択することができます」
また、SCOTが蓄積したデータを後進育成に役立てることも可能。「そのために、今、私たちは、治療のポイントを『コメント』としてSCOTに記録しています。多くの医師のナレッジを集積することで、極めて充実した“デジタル教科書”を作ることができると考えています」と村垣氏は言う。
このようなSCOTの持つ可能性を拡大していく意味でも、村垣氏が期待しているのが、自身がアドバイザーとして参加している「サステナブル・スマートシティ・パートナー・プログラム(SSPP)」だ。
これは、ICTを活用したスマートシティなど、地域社会・経済活性化やWell-Being、地域住民の幸せのための新しいまちづくりについてさまざまな人や企業が議論を行ったり、共創してイノベーションに向けた取り組みを行ったりする場を提供するプログラム。「『知の紡ぎあい』が1つのテーマとなっているように、さまざまな方の意見を聞くことができる貴重な機会。既に数人のアドバイザーの方とお話をさせていただきましたが、本当に刺激的です。例えば、SCOTのようなインフラは標準化が前提となりますが、インフラは共通化されても、都市はどこも同じではありません。それぞれの都市が特色をしっかり出すこともサステナブルの条件の1つだと思うのです。その地域や都市の特色をどうやって出していくのか。皆さんがどんな意見を持っているのかなど、興味は尽きません。そもそも、スマートシティの捉え方自体が千差万別です。医療の立場からスマートシティとはどんなまちかと問われると、私は『住んでいると知らず知らずのうちに健康になるまち』とイメージします。一方、SSPPのほかのアドバイザーの方は『知恵のある人達の暮らすシティ』だとおっしゃっていました。とても素敵ですよね。互いに違う視点の意見に耳を傾けることが、新たな発想、さまざまな分野での共創につながる。私の専門である医療にも必ず役立つと感じます」
「将来的には、すべての医療機関にSCOTを配備したい」と村垣氏は続ける。世界に先駆けて超高齢化社会を迎える日本のサステナビリティを実現する上で、今後、医療の果たす役割はさらに大きくなっていく。ICTやデータの力で、医療、そして、私たちの健康管理を大きく変えるSCOTは、医療という枠組みを超え、新しいまちづくりのためのキーシステムとして、さらに注目を集めるはずだ。
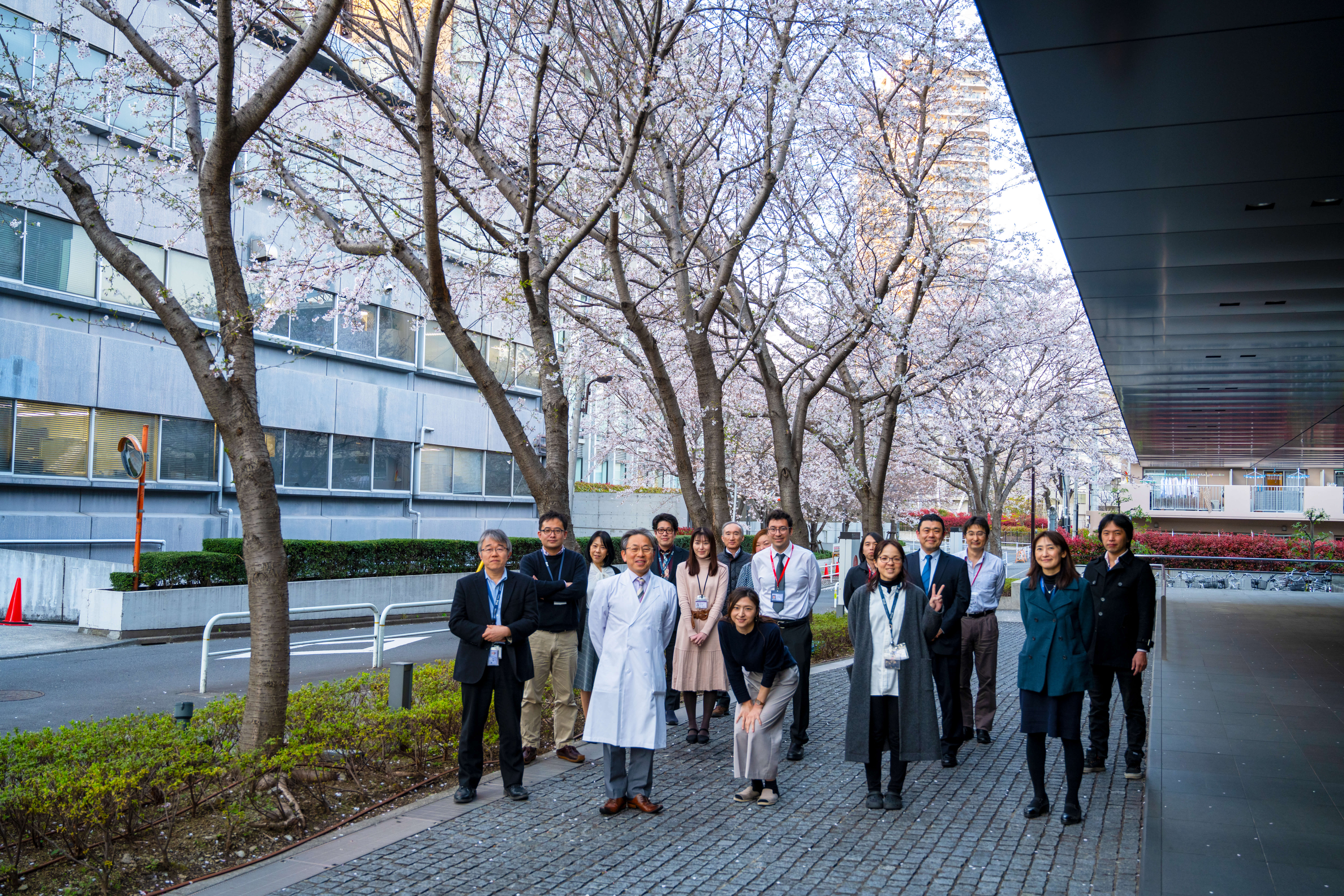
SCOT開発の中核となった東京女子医科大学のメンバーと村垣氏
医師と工学者が医工融合研究を行っている先端工学外科を中心に、5大学11企業の100人をこえる研究者が、AMEDプロジェクトを推進した(東京女子医科大学・早稲田大学連携先端生命医科学研究教育施設 通称TWInsの前で)