人を中心にした“まちづくり”
車いすマラソン大会と共に40年
大切なのは「当たり前」を続けること
さまざまな人々がすべて分け隔てなく暮らしていくことのできる「共生社会」は、これからのまちづくりで欠かせないテーマの1つである。これについて、1981年から約40年にわたり「大分国際車いすマラソン」を大分県と共に開催するなど、バリアフリーへの先駆的な取り組みを続けてきたのが大分市だ。この大会の開催を通じて、同市がかたちづくってきた共生社会の姿とは。大分市職員として、その実現に尽力してきた2人に話を聞いた。(取材時期2020年9月)
【※この記事は全2回中の1回目です】
目次
- 世界に先駆けてスタートした、車いすだけのマラソン大会
- 世界中からトップクラスのパラアスリートが大分に集結
- 車いすマラソンは、すでに「あって当たり前」の存在
- 「個のつながり」をベースに、同じ熱量で継続していく
- アスリートの本気の勝負を見れば、必ず応援したくなる
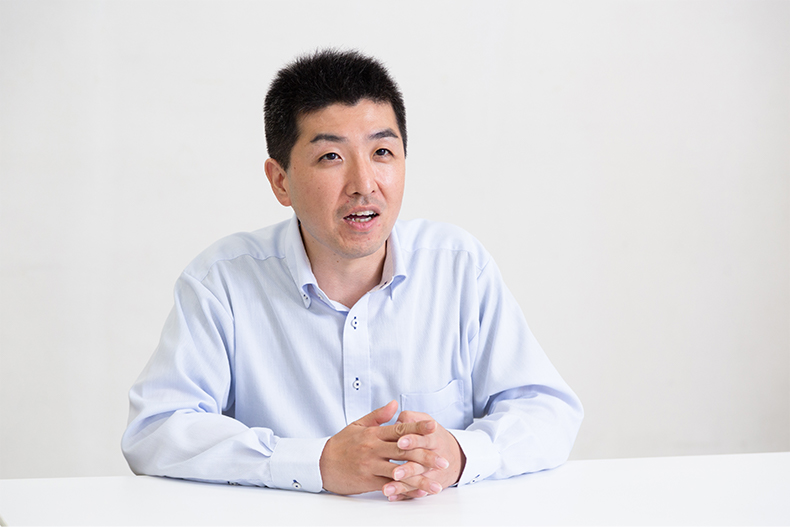
大分市 福祉事務所障害福祉課 医療・手当給付担当班 主査
利光 孝行氏

スターアイテム 代表
藤井 智宏氏
世界に先駆けてスタートした、車いすだけのマラソン大会
大分県中部に位置する大分市は、豊かな自然と天然の良港に恵まれ、古くから東九州最大規模の経済拠点として栄えた土地である。戦国時代にはキリシタン大名の大友 宗麟がこの地を治め、全国に先駆けてヨーロッパ文化を移入。日本で初めて宣教師養成学校(コレジオ)や西洋式の病院が作られるなど、南蛮貿易の拠点として隆盛を誇った。
高度成長期には九州を代表する工業都市として急成長し、名実ともに東九州最大の拠点都市となった大分。その、もう1つの顔はサステナビリティ先進都市といえるだろう。中でも、障がい者支援の取り組みは全国的に有名で、障がいの有無を越えて人々が支え合う「共生社会」の実現に向け、先駆的な取り組みを行ってきたことで知られている。
例えば、同市は1998年に、総合的かつ計画的な障がい者支援策の推進を目的とした「大分市障害者計画」を策定。その後、「第二期大分市障害者計画改訂版」(2008年)、「第三期大分市障害者計画」(2013年)、「第三期大分市障害者計画改訂版」(2020年)へと内容の見直しを進めながら、障がい者の自立と社会参加に基づくバリアフリーなまちの実現に向け取り組んできた。
また近年は、バリアフリーやノーマライゼーションへの社会的な関心の高まりを受けて、国の障がい者施策も進展を見せている。「障害者総合支援法」「障害者差別解消法」といった新たな法律の施行と連動するかたちで、大分県や大分市の障がい者支援策もさらに拡充されている。
その一例が、大分県が2016年4月に施行した「障がいのある人もない人も心豊かに暮らせる大分県づくり条例」だ。ここでは、「人が障がいの有無によって分け隔てられることなく、人生のあらゆる場面で相互に助け合い、支え合う社会をめざす」ことを県の願いとして掲げている。また大分市も、2020年6月に策定した「第2期大分市総合戦略」の中で、2024年までの取り組みの目標を提示。それによると、「就労支援サービス利用者数」は2018年比で約1.2倍、「就労支援サービス利用から一般就労への移行者数」は同・約1.4倍をめざすとしており、これからも障がい者との共生に一層尽力していくことを明らかにしている。
加えて、これらの動きと表裏一体で、連綿と続いてきた取り組みもある。それが、毎年11月に大分市内で行われる「大分国際車いすマラソン」である。この大会は、1981年の国際障害者年を記念して、世界初の「車いすだけのマラソンの国際大会」としてスタート。以来、大分県および複数の組織・団体との共催により、産・官・民が全面的に連携しながら大会を開催してきた。

【写真】緊張感のあるスタート地点の様子
障がい者スポーツの普及は、多くの自治体が直面している問題だ。大分県と大分市はなぜ、この世界屈指の障がい者スポーツイベントを育て上げることができたのか。元大分市職員で、2020年1月に独立してサステナビリティをテーマとした会社を立ち上げた藤井 智宏氏は次のように話す。
「大分国際車いすマラソンは、社会福祉法人『太陽の家』を開設した医学者・中村 裕博士の存在を抜きには語れません。中村博士は日本の障がい者スポーツ振興の草分け的存在で、1964年の世界的スポーツイベントでは日本選手団団長も務めました。その中村博士が、『保護より機会を!』という思いのもとで立ち上げたのがこの大会です」
世界中からトップクラスのパラアスリートが大分に集結
太陽の家が別府市に開設されたのは1965年のことだ。その後中村博士は、「世に心身障害者はあっても仕事に障害はあり得ない」という信念に基づき、ソニーやホンダ、オムロンなどの企業の経営者を説得して共同出資会社を設立。多くの重度障がい者を雇用し、障がい者の自立と共生社会の実現に向けた地域の取り組みに先鞭をつけた。
また博士は「福祉のまちづくり」を提唱し、障がい者スポーツの振興にも尽力した。1961年の「大分県身体障害者体育大会」開催、海外で行われる障がい者スポーツ大会への参加支援などに取り組んだのち、1981年に大分国際車いすマラソンを立ち上げた。
大会創設後は、車いすマラソン界の“レジェンド”であり、この大会で現在の世界記録(2020年10月現在)を出したハインツ・フライ(スイス)選手やマニュエラ・シャー(スイス)選手を筆頭に、世界のトップアスリートが大分に集結。大分国際車いすマラソンは、名実ともに世界最大規模・最高峰の大会の1つに成長した。
大会を支えているのがボランティアスタッフの頑張りだ。例えば通訳。海外選手が来日すると、大分空港に到着してから、滞在中のショッピング、大会当日、そして帰国チケットの手配まで、ボランティアが1対1で手厚くサポートする。
「選手も居心地が良いようで、『大分に来るのが楽しい』『また来年も来るね』といった声をよく聞きます。招待ではなく自費参加の選手も、『旅費を払ってでも来たい』と言うほどです。現在は毎年約50~80人の通訳ボランティアが活躍しており、英語以外の言語にも対応できる体制ができています。こうしたボランティアの頑張りがなければ、大会をここまで大きくすることは難しかったでしょう」と藤井氏は言う。

【写真】ボランティアと車いすマラソン選手のふれあいの様子
車いすマラソンは、すでに「あって当たり前」の存在
もちろん、成功要因はボランティアの活躍だけではない。自治体の職員や協賛企業の社員、地元住民もまた、一丸となって大会を支えてきた。
例えば、大分市の職員も、大会前後と期間中は、レース運営や自治会への協力要請など、裏方の仕事に奔走する。大分市民も、大会前後での来日選手との触れ合いや、コース近隣の交通規制への協力などを通じて、スムーズな大会の実施・運営を支えてきたという。
このような小さな協力の積み重ねが、レジェンド級の選手を惹き付け、彼らに憧れる若いアスリートも呼び寄せた。それが、大分国際車いすマラソンを世界最大規模のスポーツイベントにした理由の1つなのだろう。
「大分市では、40年という長い年月を経て車いすマラソンが市民の間に浸透し、今では『あって当たり前』の存在になりました。はじめは中村博士という1人の熱意でスタートした大会が、何度も繰り返し開催される中で、まちの文化になったのです。現在の大分市では、障がい者スポーツがなんら特別なものではなく、市民の日常の一部になっていると感じます」と大分市職員の利光 孝行氏は述べる。
大会のシーズン、早い選手は2週間前から大分入りして河川敷などで練習を始める。商店街には通訳を伴った外国人選手が訪れ、品物を手に店主と笑顔で会話する。その光景に、市民は「もうそんな時期か」と季節の移ろいを感じ、「今年も車いすマラソンが始まるね」と挨拶を交わす。ここでは、車いすの選手の姿がまちに溶け込み、季節の風物詩となっている。一過性のイベントとしてではなく、地域の年中行事として馴染んでいる点が、この大会の特色といえるだろう。
「個のつながり」をベースに、同じ熱量で継続していく
また大分市は、この大会の運営実績などが考慮され、2021年に東京で予定されている世界的スポーツイベントの「先導的共生社会ホストタウン」(以下、共生社会ホストタウン)の指定を受けた。このスポーツイベントに参加するため来日するスイスのパラアスリートを受け入れる予定だ。
この共生社会ホストタウンが備えるべき考え方の1つに「心のバリアフリー」がある。これは、単に宿泊施設などのインフラを整備するだけではなく、住民や企業の十分な心構えも重要だということである。実は、ほかの自治体の多くが苦労するのが、この心のバリアフリーの実現なのだという。
「先日、共生社会ホストタウンの会合があった際も、ほかの自治体から多くの質問を受けました。『大分では、なぜ選手と住民の交流がうまくいっているのか』『どうやって信頼関係を築いたのか』など、その多くが心のバリアフリーの実現にかかわるものでした。私たちにとっては、当たり前過ぎてうまく言葉にすることが難しいのですが、個人的には、長年蓄積したノウハウを基に、毎年変わらない“熱量”で繰り返し実践することが1つのポイントなのではないかと考えています」(利光氏)
藤井氏も続ける。「私も、利光さんの意見とほぼ同じです。例えば、大分国際車いすマラソンでは、毎年同じスタッフが同じ選手を空港で出迎え、『今年もがんばって』と声をかけます。そうすることで、ノウハウを蓄積しつつ、毎回同じ熱量で選手をサポートすることができるのです。継続する中で、単に運営にかかわる知識やテクニックを蓄積するだけではなく、『個のつながり』を強固にしていく。これが重要なのではないでしょうか」。
個のつながりが生まれれば、選手と大会との絆も深まっていく。「参加したい/走りたい」「サポートしたい」という互いの思いが大きな熱気となって大会全体を包んでいき、良い循環につながっていくという。
アスリートの本気の勝負を見れば、必ず応援したくなる
サポートする側の市職員や市民の熱量を維持するには、どうすればよいのか。これについては、やはりスポーツなので、「アスリートの本気の勝負を目の当たりにすること」がカギになる。
「大会を少しでも観たり、運営にかかわったりするチャンスがあれば、絶対に次が楽しみになります。『去年1位になったあの選手、今年も来るかな』『今年はゴール地点で観戦したいな』と、新たな興味が次々湧いてくる。すると自然に、大会自体のことを好きになり、応援したくなるはずです」(藤井氏)。これは、スポーツ自体が持つ素晴らしい力の為せる業といえるだろう。そこに障がいの有無は関係ないのだ。

【写真】第39回大会(2019年)表彰式の様子
「当たり前」を続けるという考えに基づき、コロナ禍に見舞われた今年2020年も、規模を縮小して大会を開催する予定だ。それが来年、再来年へのステップになり、連綿と培ってきた共生社会への取り組みを未来へつなぐ架け橋になる。車いすマラソンを通じて紡ぎ上げた、個と個のつながり。人肌の温もりを帯びた絆こそが、心のバリアフリーを広める一番の近道だということを、大分市の事例は物語っている。
(後編)デジタルのマップで便利を見える化市民と共に次代の共生社会をつくる