アドバイザー活動紹介
「公・民・学連携」と「データ」の可能性を追求し地域に応じた魅力的なまちづくりを推進したい
コロナ禍でリモートワークが普及し、人流シフトによる都心からの流出と地元回帰が始まりつつある。そうした中、都市やまちのあり方も大きな変貌を遂げつつある。Withコロナ時代のまちづくりに求められるものとは何か。地域に応じた魅力的なまちづくりを推進するためのカギはどこにあるのか。都市デザインを専門とし、公・民・学連携によるまちづくりを提唱・実践する、都市計画学者であり都市デザイナーである出口 敦氏に話を聞いた。
(取材時期:2021年7月)
目次

東京大学 大学院新領域創成科学研究科 教授
出口 敦氏
東京大学工学部都市工学科卒業、1990年同大学院博士後期課程修了(工学博士)。九州大学助教授、教授を経て2011年東京大学教授に就任。現在、柏の葉アーバンデザインセンター(UDCK)のセンター長として、柏の葉における公・民・学連携による国際学術研究都市・次世代環境都市づくりに取り組んでいる。
コロナ禍で“生活圏”に注目が集まった
新型コロナウイルス危機はさまざまな方面に大きな影響を与えた。それは都市計画も例外ではない。「今、コロナ禍で見直されているのが、パリの“15分都市圏”構想など徒歩圏スケールの再生です」と出口氏は語る。
“15分都市圏”とは、昨年6月のフランス地方選で、パリのアンヌ・イダルゴ市長が公約として打ち出した計画である。2024年までに「誰もが車を使わず、徒歩や自転車で15分以内に都市機能にアクセスできるまちをつくる」というのがその内容だ。
「この1年は、自宅周辺の環境、すなわち“生活圏”がものすごく注目された時期でもあります。徒歩圏内に気に入った店や公園があるか、自分のやりたいことを、仲間と一緒に実現できるような環境かどうかという点に関心が集まり、都市やまちにおける“生活圏”としての側面が注目された。今、まさに求められているのは、自分の手でつくり上げることのできる環境です。自分たちの手が届く範囲で、自分たちがやりたいことを実現できる場所――それが、コロナ危機を経験する中で芽生えてきた都市やまちの考え方の一つだと思います」
さらにいえば、生活圏への関心が高まるにつれて、人々が都市に求めるニーズにも変化がみられるという。従来は、「いかにして集客し、賑わいをつくり出すか」が大きなテーマだった。だが、在宅での生活が長引くにつれて、人々は、読書や勉強、趣味に没頭できるような、「一人でいられる場所」が案外少ないことに気付かされた。
「これまで、都市の中心テーマは『大勢の人を集めて楽しむエキサイティングな場』でしたが、コロナ禍を経て、『一人でいられることを保証する場』としての意味が見直されつつある。自分の生活圏の中で、自己実現できるまちであってほしい、という新たなニーズが生まれつつあると思います」と出口氏は語る。
公・民・学連携を成功させるカギは「学」の存在
人の動きが都心から生活圏へと移行しつつある中、まちづくりの現場でも、より地域ニーズにきめ細かく対応することが求められている。そのカギを握る手法として、出口氏らがアーバンデザインセンター(UDC)の取り組みを通じて提唱してきたのが「公・民・学連携」だ。これは、公(行政や非営利組織)・民(民間企業や住民)・学(大学や専門家)の三者が、連携して課題解決に取り組むコラボレーション手法のことを示している。出口氏がセンター長を務めるUDCKでは、“学”の立場から、先進的な公・民・学連携による国際学術研究都市・次世代環境都市づくりに取り組んできた。
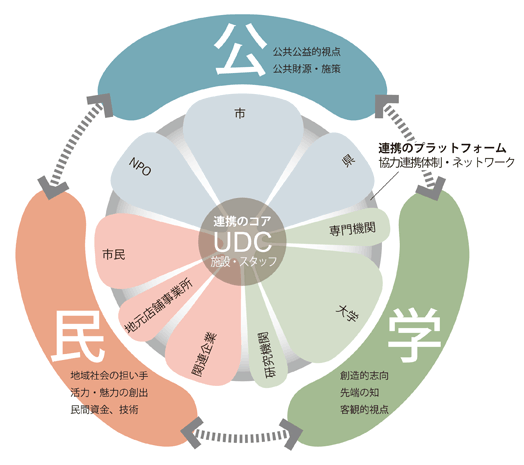
図1:「公・民・学連携」のイメージ 提供:柏の葉アーバンデザインセンター(UDCK)
これからのまちづくりでは、「公」「民」「学」それぞれの立場で活動する個人や組織が、協働して課題解決にあたるコラボレーションの仕組みづくりがカギとなる。
参考:UDCK(柏の葉アーバンデザインセンター)センター長(出口敦)挨拶
https://www.udck.jp/about/000245.html
「公・民連携の中に“学”が入ることは、さまざまな意義があります。専門家がプロジェクトの調整役を務める、技術や知見を提供する、といったこともその一つですが、さらに重要なのは、一つのまちに長く関わることができるという点です。自治体や企業では、数年ごとに人事異動で担当者が交代することが少なくありません。しかし、まちづくりは10年単位の時間を要する仕事です。“学”が入れば、短期的な採算性だけにとらわれず、長期的な視点で進めることができますし、これまでの経緯にも配慮しながらまちづくりを進められます。また、学生が関わることによって、若い世代の視点を取り入れることができる点も大きなポイントです」
こうした公・民・学連携による成果の一つに、「柏の葉かけだし横丁」(千葉県柏市)がある。
これは、2015年秋にUDCKと出口研究室、三井不動産が共同で行った社会実験、「柏の葉賑わいづくりプロジェクト」から生まれたものだ。同プロジェクトでは、当時、飲食店が少なかった柏の葉キャンパス駅前の飲食需要を探るため、数回にわたる社会実験として「屋台村」を開設した。期間中は、地元や近隣から、ファミリー世帯や就労者など多くの人々が集まり、この地域に大きな飲食需要が存在することが明らかとなった。
これが発端となって、関係者で構想を練り、三井不動産が鉄道高架下のインフラ整備を行った。2018年9月に『柏の葉かけだし横丁』がグランドオープンし、その後約20軒の飲食店が軒を連ねる。「新しいアイデアが公・民・学連携による社会実験を通じて検証されたことで、まちの一つのシンボルとして実現された。その意味で、『柏の葉かけだし横丁』は、公・民・学連携によるまちづくりがかたちになった一つの例といえます」(出口氏)。

図2:柏の葉かけだし横丁 提供:三井不動産株式会社
2018年9月、柏の葉キャンパス駅北側の鉄道高架下にオープンした。公・民・学連携による社会実験「屋台プロジェクト」から生まれたものだ。飲食店を中心に約20店舗が営業し、地域の賑わいを生み出してきた。ただ、コロナ禍で市内の他の飲食店と同様に店舗の営業は制限され、厳しい状況にある。
まちづくりに“学”が果たす役割は、それだけにとどまらない。まちづくりの現場では、往々にして利害の対立が起こり、プロジェクトがなかなか進捗しないといった事態が生じがちだ。「その調整においても、“学”が関わることへの期待は大きい。地元の大学や高校が積極的に関わることが、公・民・学連携を進めるポイント」だと出口氏は強調する。
データの利活用が行動変容をもたらす
現在、柏の葉では、エリアマネジメントを積極的に展開する地域運営の仕組みづくりも行っている。エリアマネジメントとは、地域の特性に合った魅力的なまちづくりをするために、住民や事業主、地権者などが主体的に行う取り組みのこと。「地域の課題を解決し、エリアマネジメントを効果的に進める意味でも、今後はデータの利活用がますます重要になる」と出口氏は言う。
「データを活用する最大の理由は、それが『行動変容をもたらす』ということです。住民にとって安全で魅力的なまちをつくるためには、地域の方々に、さまざまな情報を分かりやすくかつリアルタイムで提供することによって、行動変容を促す仕組みが必要です。例えば、柏の葉では、まちの中にセンサーを設置するなどして、さまざまなことに役立てるスマートシティの取り組みを進めています。センサーで収集したデータを活用すれば、気温や湿度を観測して熱中症対策につなげたり、人の流れを可視化して密な状況を回避したり、防犯に役立てたりと、さまざまな目的で活用することができる。こうした行動変容につなげていくことが、データ活用の意義だと考えています」
データの利活用によって、地域の状況が可視化されれば、住民が必要とするサービスを提供することも可能になる。それがスマートシティのめざすところでもあるが、事はそう簡単ではない、と出口氏は警鐘を鳴らす。
「データの利活用を進めるためには、異業種の企業同士が、互いにデータを共有することが必要です。例えば、バス会社が持つ人の移動データや、商業事業者が持つ購買データなどを組み合わせれば、さまざまなサービスが可能になる。ところが、データの提供に対する企業の抵抗感は大きく、行政側もリスクを恐れて、なかなかデータを出そうとしない。このままだと先に進まないので、まずは“手あかがついていないデータ”、例えばIoTセンサーが未整備でデータ化されていないようなものを、研究機関がデータ化し、組み合わせていくことも一つの方法だと思います。データ・プラットフォームに巨額の投資をするよりも、共有できるデータからどんどん組み合わせて、徐々に拡張していく。その方が、データの利活用もうまく進むのではないかと思います」
中でも、出口氏が期待を寄せるのが、ICT/IoTの活用により「近未来の予測が可能になる」という点だ。
「ICT/IoTによって地域の状況がデータ化されネットワークでつながれば、我々が生きているこの瞬間が、時々刻々とデータ化されていく。そのデータを使って、3分後、30分後の未来を予測できるようになれば、それは大きな行動変容をもたらすでしょう。今、我々は人口予測に基づいて、10年後の世界を予測し、都市計画をつくっています。その方法論はある程度確立されていますが、3分後、30分後の世界を予測することは難しい。でも、30分後に発生する災害を予知できれば、人命を救える可能性もそれだけ高くなる。ICT/IoTの活用で、近未来の予測が可能になれば、新しいサービスが生まれ、我々の生活を大きく変えることになると思います」
データによって まちの魅力を磨き上げる
近年、スマートシティ計画において、「Well-Being」をまちづくりの指標として導入する動きが広まっている。だが、「今、Well-Beingを測る指標として打ち出されているものは、ヨーロッパなどの先進地域でも従来型の指標が多く、新しいものが確立しているとはいえません」と出口氏は言う。
「従来の都市計画では、主に都市を空から見て評価してきました。例えば、空から地上を見て、緑がどれだけ増えたか、道路ネットワークがどれだけ充実したか、といったことを評価するわけです。その延長線上で、『公園の面積が増えれば増えるほど、住民は幸福になる』と考えるのが、今のWell-Beingの指標です。しかし、公園の面積が増えたことにより、本当に住民のWell-Beingが向上したのかどうかはわからない。要するに、空からスマートシティを眺めても、住民がどんな行動変容を起こしたか、どのぐらい健康になったかは見えてこない。Well-Beingを測るためには、“人間”を直接測り、QoL (Quality of Life) を評価する必要があるわけです。しかし、この分野における研究はまだ進んでいない。その手法を確立するべく、我々も研究開発に取り組んでいるところです」
SSPPへの参加を好機として、公・民・学連携のさらなる可能性を追求したいと語る出口氏。
「地域の資源を活用して、リアルな空間を魅力的にデザインすることが、私の専門領域。どんなまちにもその地域ならではの資源があり、眠っている資源を掘り起こし、地域の人たちと一緒に新しい魅力をつくり上げることが、我々の役割だと考えています。とはいえ、“つくって終わり”ではなく、我々がデザインした空間を、魅力的で使いやすい環境として管理し、利活用していかなければならない。そのときに役立つのが『データ』です。デザインされた環境をデータを使ってマネジメントし、地域の方々が利活用することを通じて、その価値をさらに高めていく。その一連の仕組みを、自治体や企業とコラボレーションしながら創り出していければ、と考えています」と今後に期待を寄せた。